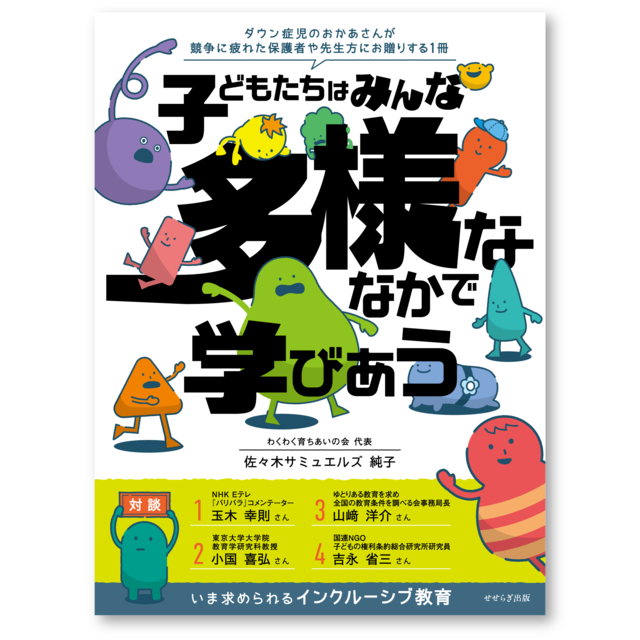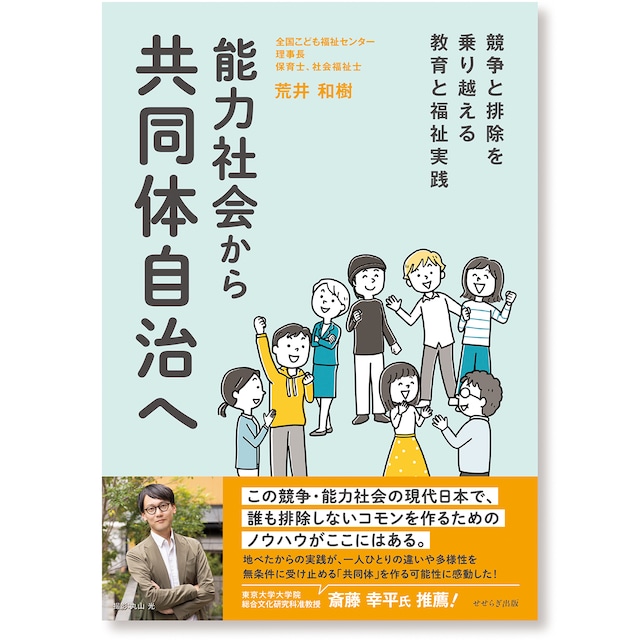人権問題としての「教育」疎外児童・生徒
■サイト■
https://community-publishing.net/kyoiku_sogai/
試し読みはこちら↓
https://community-publishing.net/comi/wp-content/uploads/2025/11/kyoiku_sogai_trial.pdf
------
クレジットカードによるご購入は、注文をいただいてから3営業日以内に発送いたします。
コンビニ決済、銀行振込の場合は、入金を確認してから3営業日以内に発送いたします。
※PAY ID以外でのご購入(クレジットカード・コンビニ決済・銀行振込等)の場合は、「ゲストとして購入」ボタンから進んでいただき、お名前やご住所等を入力してください。
------
本書は、近年、教育と社会から疎外される子どもたちの深刻な荒みや自尊感情の喪失状況に着目し、その多様な要因の中から、とりわけ現在の学校教育・制度に内在している「一定」に基づく画一的な教育によって、事実上その「教育」から疎外や排除を受けている児童生徒がいること―そして、その子どもたちは、結果的に憲法二十六条の保障を享受しているとは言い難い状態で放置されている事態を、人権問題として提起するものである。
この問題解決に臨む基本的立場として、当該状況を、改めて子どもの立場から捉え直す視座の転換を行い、大人の都合で権利を肩代わりすることなしに、子ども自身によって、能力に応じた「教育を受ける権利」の保障として教育制度整備要求を行えることを提起する。具体的に、能力に応じた「学習要求」を可能にする制度創設の提起を行うことが目的である。同時に、制度創設を可能にする憲法上の理論的検討を学習権の今日的意義を明らかにしながら、また、子どもの権利条約の国際解釈を用いながら検討する。(「本書の概要」より)
【本書の概要】
序 章
1.本書の目的と背景
2.児童生徒の問題事象に対する視座の転換
3.教育現場を取り巻く潮流
4.「相対化」を可能にする価値原理
第1章 教育における一つの現実
第2章 教育と憲法の関係と位置づけ
第3章 教育を受ける権利と学習権との関係
第4章 学習権の利益とは何か
第5章 教科書裁判・学力テスト裁判での学習権の用いられ方
第6章 学習権の曖昧さへの回答試論
第7章 「学習要求」の国際的な位置づけへ
第8章 国際的な教育の人権性の広がりと学習権の今日的意義
終 章 ― 結論と提案 ―
結 論/提 案/あとがき